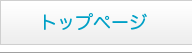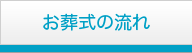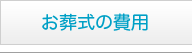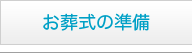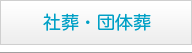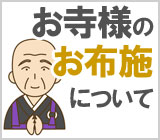葬儀の流れ

お医者さんからの危篤の判断があった時には、本人が最期に会いたいと思う方、
また、家族が会っておいて欲しいと思う方々に連絡をします。
親子、兄弟姉妹であれば、普段は疎遠になっていたとしても連絡を入れる方がよいでしょう。
親戚の方への連絡は、本人との普段のお付き合いの深さを考慮してですが、なるべく連絡をします。
親族以外でも、本人が会いたいと思っている人には連絡をします。
深夜・早朝でも状況が状況ですので、一言断りを入れてその上で、端的に伝えます。
電話がもっとも有効な連絡方法ですが、連絡が取れない場合は、ファックスや電報(115)でも連絡をすることができます。

現在はほとんどの方が病院で最期を迎えられます。
亡くなられた瞬間は何も考えられず、心が空虚になります。
そうした時に、これからの搬送や葬儀の手配について考えなければなりません。
そのことは葬儀社側でも分かっていて、細心の注意を払って対応をするよう努めていますが、
あまり良心的でない葬儀社だと、その状況を利用しようと考えることは想像に難くないことです。
臨終の時から葬儀後までになすべきことすべてを知っていて、尋ねることになるのは葬儀社の人ですので、
親身になって対応してくれる担当者と出会うことができれば心の不安が少しでも解消されるでしょう。
心当たりの葬儀社がある場合は、連絡をとり、寝台車でご遺体をご自宅もしくは、安置場所へと搬送します。
葬儀社の心当たりがない場合に、病院からも搬送だけでもと、葬儀社を紹介してくれる場合もありますが、
病院でもそのサービス内容を正確に把握して紹介しているわけではないですので、
安易にすべてを任せてしまうことで、後々のトラブルになることもございます。

安置場所を決めます。
病院提携の葬儀社に搬送を依頼した場合でもその葬儀社は搬送のみの依頼とし、 葬儀の施行は、変更が可能です。
事情があってご自宅にお帰りできないときは斎場に直接安置もできます。
病院からご自宅、または直接斎場へ寝台車でお送り致します。
自宅または斎場まで搬送したご遺体を安置いたします。
安置後は、経机、仏具、線香、ロウソク、枕花、供物、水をお供えして枕飾りをします。
準備が出来たら血縁の近い方からお参りしていただきます。
菩提寺に連絡を入れ枕経の手配をします。
(菩提寺のない方は、当センターで寺院の手配もいたします。)

●ご家族と葬儀社とで、葬儀の場所・規模・形式・日程などを打合せ
(どのような葬儀にしたいのかをしっかりと葬儀社へ伝えましょう)
●見積りを受け取る
●喪主を決める
●親族の人数の確認
●菩提寺がある場合は連絡を入れて都合を確認し、読経の依頼をする
心身ともにお疲れの時だとは思いますが、ご家族、葬儀社との打合せが肝心です。
自分たちの要望・希望をしっかりと伝えます。
葬儀の場所・規模・形式・日程を決めて、見積もりも併せてとってもらうようにしましょう。
動揺もしているときです。一人や二人、冷静な方を打合せの場に立ち会って頂くと良いでしょう。

納棺はいつ行うか、ご遺族と葬儀社さんで相談の上、日時を決めます。
お亡くなりになられた翌日に納棺を行い、その翌日にお通夜という場合や、お通夜の前にされる場合など様々です。
納棺し、棺のふたを閉めたら全員で合掌し、納棺の儀とします。

●葬儀社が式場での装飾(祭壇等)をする
●通夜が終わると葬儀社と告別式の打ち合わせをする
●お寺様を呼ばれた場合はお布施を通夜にお渡しする
(必ずしも決まっていることではありません)
現在では一般的に通夜に弔問客が来るのがほとんどです。
弔問客には出来るだけ焼香が終わりましたら通夜振舞いをしていただきましょう。
弔問客全員焼香が済み、僧侶が祭壇前から退席をしたら、遺族も通夜振舞いの席へ移動し、感謝の意を述べます。 通常1時間くらいです。

●最後のお別れをする
●喪主の挨拶
●棺を霊柩車へ移し、親族はマイクロバスにて火葬場へ移動
(斎場での葬儀で、移動が不要な場合は、マイクロバスは必要ありません)
告別式は、故人の遺族・友人・知人が最後のお別れをする時間です。 心ゆくまでお別れをなさってください。
出棺前に喪主が挨拶を行い、その後喪主や遺族の中で血縁の濃い人が位牌・遺影をもちます。

●火葬許可書を提出して荼毘にふす(葬儀社に代行していただけます)
●棺を火葬炉に運び、焼香・合掌
●お骨拾い
●埋葬許可証を火葬場から発行してもらう(大切に保管をされてください)
火葬場に到着をしたら、まず火葬許可書を提出します。
(一般的には葬儀社が代行していただけます)
霊柩車から棺を出して火葬炉に運びます。喪主以下全員で焼香・合掌をいたします。
このときに僧侶に経を上げていただくことも出来ます。火葬をしている間は休憩室で待機します。
お骨上げになりますと、案内が入りますので、お骨を上げるときは足元から二人一組で骨壷に入れましょう(一般的な例)。
終わりましたら、火葬場から埋葬許可書を頂いて帰ります。(基本的に骨壷の中へ埋葬許可書を入れてくれます)
※埋葬許可書は納骨のときに必要な書類です。大切に保管をしてください。

●後飾り祭壇にご遺骨を安置し、ご住職をお迎えして読経をいただきます。
●ご住職に「お布施」をお渡しします。
●初七日法要終了後、事前に準備した引き物(粗供養)を参列者へお渡しします。
慌ただしい現代社会では、親族が遠隔地にも多くなった事と、多忙な方が増えているため、
初七日法要はご住職に相談し葬儀当日、お骨上げ後に行うことが多くなりました。

近隣や親戚などお世話になった方々へのお礼等、お葬儀後の後片付けは大変なものです。
国民年金手帳・健康保険証等の抹消手続き、世帯主の変更等、役所への届け出(亡くなった日から14日以内)は早めに行ってください。
自宅飾りの片付け・集金等に関しましては、担当者と事前に打ち合わせください。
忌明け・初盆・一周忌等、故人様に対する思いを、期日を区切って形にあらわすものが、法事・供養です。
【法要】
年忌表〈神式・キリストでは異なります)
一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、
五十回忌、百回忌。一般には、三十三回忌までというように、途中を略すなどさまざまです。
【忌服期間】
忌の期間は死後忌明けまで、服の期間は死後一カ年とされています。
【忌服期間に注意すること】
喪中(死後一年以内)には、結婚式などのめでたい席に臨む事や、神社へ参拝する事も控えるのが通例です。
正月の飾り付け、年始回り、年賀状等も控えます。